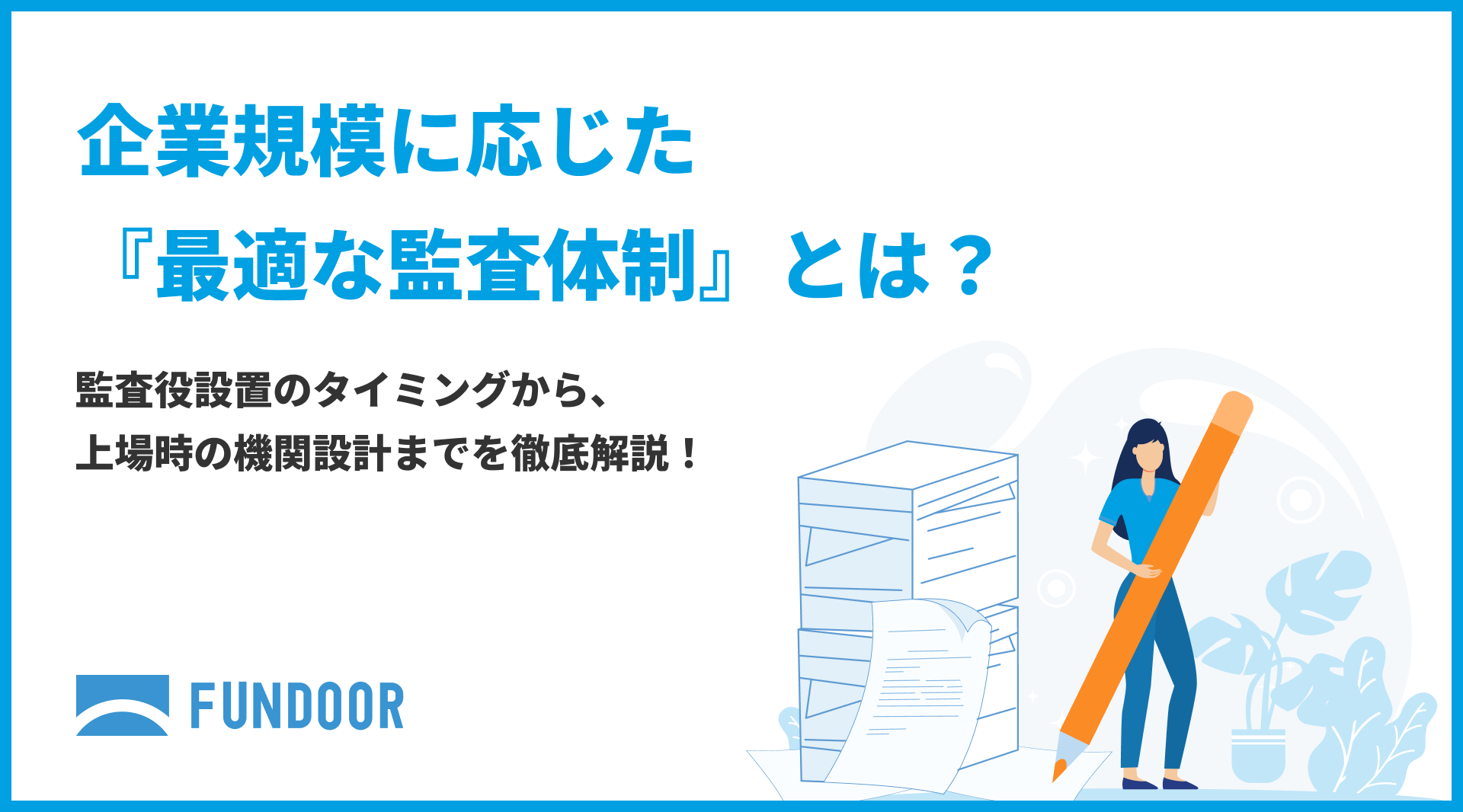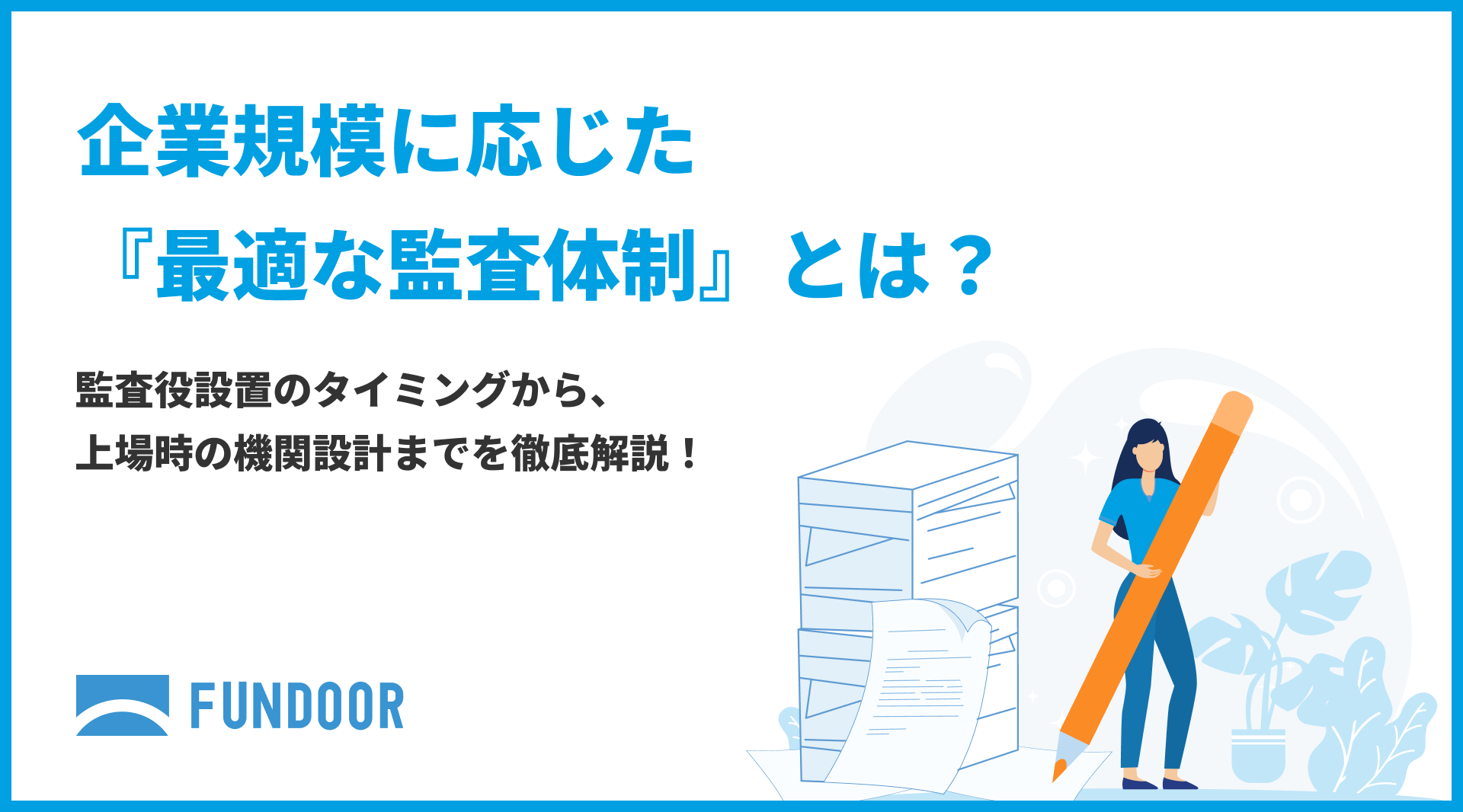
監査役、監査役会、監査等委員会……そんな言葉を耳にするものの、その名称はどれも似ていて「何が異なるのか分からない」という人も多いかもしれません。
「企業が成長していく過程で、監査役はいつ必要になる?」
「監査役会や、監査等委員会を設置するタイミングはいつ?」
といった疑問を機関設計の全体像から解説し、それぞれの違いについて詳細を解説していきます。
※本記事は、上場準備中のスタートアップ経営者・担当者に限らず、監査体制について改めて基本から押さえたい方向づけの内容になっています。
<経営管理プラットフォーム「FUNDOOR(ファンドア)」がお届けします>
1.監査体制の設計ステップを、図解で解説!
企業が成長していく過程において、「監査役」の存在は信頼性の高い組織を築くための重要な土台となります。
監査役、監査役会、監査等委員会がどのタイミングで必要とされるのか、それがわかりやすいスタートアップを例に、下記の図で示しました。

Step1.創業期
「Step.1 創業期」では、取締役会を設置していないスタートアップ企業が多いため、それに併せて監査役を置いていないケースがほとんどです。高成長を目指すスタートアップでは、設立時には監査役を置かない方がスピード・コスト・柔軟性の面で有利、かつ合理的と判断されています。
Step2.成長期
創業後、事業が軌道に乗ると、さらなる事業拡大を目指して資金調達を検討するスタートアップも多いでしょう。VCから資金調達を行い、初めて「取締役会」を設置するタイミングを「Step.2 成長期」としました。
取締役会設置会社では、取締役を三名以上置くことが決められていることはもちろん(会社法第331条第5項)、監査役を置く必要があります。(会社法第327条第2項)。
創業期には監査役を置いていなかったスタートアップも、この時に初めて監査役を置く必要に迫られます。
Step3.上場準備期
そして、監査役を設置してガバナンスを強化しながら、IPOを具体的に目指し始める段階を本稿では「Step.3 上場準備期」としました。
上場企業(本稿では公開会社かつ、大会社を指します)は、少なくとも監査役会を設置しなければなりません(監査等委員会設置会社、および指名委員会等設置会社を除きます)(会社法第328条第1項)。また、この機関設計に追加し、会計監査人も設置しなければなりません(会社法第328条第1項)。
2.監査役の役割、選定基準とは?
ここまで、監査役、監査役会がどのタイミングで必要とされるのか、スタートアップの成長過程を例に解説をしてきました。では、監査役を置く必要性に迫られた場合、どのように選定を進めれば良いのでしょうか?
まずは、会社法で定められている『監査役に求められる役割』について、解説していきます。
2−1.監査役に求められる役割
監査役の役割をひと言で表すと、「計算書類・財務諸表に関する会計監査や、取締役の職務執行に関する業務監査、ならびに株主総会の議案等に対する意見表明をおこなう役員」です。以下、会社法で定められている『監査役の権限』になります。
会社法 第三百八十一条(監査役の権限)
1.監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
また、上記の権限を実行的に果たせるよう、以下のような強力な権限も与えられています。
・取締役が不正行為をした、または不正行為をするおそれがある場合などは、遅延なく取締役会で報告しなければならない。 (会社法 第三百八十二条(取締役への報告義務) 参照)
・取締役会に出席し、必要がある場合は意見を述べなければならない。 (会社法 第三百八十三条(取締役会への出席義務等)第一項 参照)
・監査役は、株主総会に提出される議案や書類が法令・定款に違反していないか、不当な点がないかを調査し、問題があればその結果を株主総会に報告しなければならない。 (会社法 第三百八十四条(株主総会に対する報告義務) 参照)
・取締役が法令や定款に違反する行為、またはそれらの違反行為をするおそれがあり、その行為によって著しく損害が生じるおそれがある場合などは、その行為をやめるよう請求することができる。 (会社法 第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)第一項 参照) |
会社の所有者は株主ですが、日々の経営は取締役がおこないます。
その取締役が不正を働くことが無いよう、株主の立場から独立して監督・監視する役割を監査役が担っています。
2−2.監査役の選定基準
続いて、監査役にどのような人を選定すれば良いのかについて解説していきます。選定基準については「①法律上の必須要件」と「②実務的な要件」の二つの側面から見ていきます。
【①法律上の必須要件】
以下に記載する内容は、会社法で定められている「監査役になれない人」です。これにひとつでも該当する人は、監査役になることはできません。(会社法第335条第1項、第2項)
監査役になれない人(会社法第331条第1項を参照)
・法人(会社そのものなど) ・成年被後見人または被保佐人(※特定の条件付きで就任可能) ・会社法や金融商品取引法など一定の法律に違反し、刑の執行が終わってから2年が経過しない者 ・上記以外の罪で禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで、または執行猶予中の者
また、以下の役職との兼任も禁止されています(会社法第335条第2項)
・その会社の取締役、支配人その他の使用人(従業員) ・その子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人その他の使用人(従業員) |
監査役選定において、これらの法律上の要件をクリアしていることが前提となります。その前提をクリアした上で、「②実務的な要件」を見ていきます。
【②実務的な要件】
以下に記載する内容は、監査役選定における実務的な要件です。
先の「2−1.監査役に求められる役割」に記載している会社法と重複するため、こちらでは概要のみ記載いたします。
① 公認会計士や税理士、企業の経理・財務部門での実務経験者が理想 ┗会社の財産状況に不自然な点がないか、監査役はいつでも調査する権限があります。そのため、最低限、会社の財務諸表を読み解く知識が求められます。
② 法律の知識も有する弁護士や、企業の法務部経験者が理想 ┗取締役の職務執行が法令や定款に従って正しくおこなわれているか、チェックする役割を担っています。
③ 経営・業界慣行を理解している人や、中立的な立場で不正を指摘できる人が理想 ┗①または②の専門性・知識を有するだけでなく、資質も勘案して選任するべきでしょう。 |
3.上場時に必要な監査体制とは?
ここまで、監査役の役割と選定基準について述べてきました。
未上場の段階では監査役1名体制だとしても、上場準備段階から厳格な監査体制が求められます。上場すると不特定多数の株主が増加するため、それらの株主を保護する観点からも「監査役(1名以上)」だけの体制では不十分とされているからです。
公開会社、かつ、大会社が選択できる監査体制は、以下の3つです。
① 監査役会設置会社 ② 監査等委員会設置会社 ③ 指名委員会等設置会社 |
それぞれの役割について、次項で解説していきます。
3−1.各監査体制について解説
a. 監査役会設置会社(伝統的な日本型)
日本の上場企業で長らく主流だった、オーソドックスな形態です。
業務を執行する「取締役会」と、その業務執行が正しく行われているかをチェックする「監査役会」が独立した機関として存在します。
また、監査役会を設置する際、以下の構成を満たす必要があります。
・監査役が3名以上必要(会社法第335条第3項) ・そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(会社法第335条第3項) ・監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を1名以上選定しなければならない(会社法390条第3項) |
このように、複数の監査役によって構成され、監査・監督が行われます。
【設置するメリット】
監査役会設置会社のメリットとして、下記が挙げられます。
1.社外監査役を含め、複数の監査役が監査にあたるため、経営陣からは独立した客観的な立場で監査が可能。
2.監査役はそれぞれが独立した「独任制」の機関であり、個々の監査役が必要と判断すれば、監査役会の決定に関わらず、自らの判断で調査権限を行使可能。
3.監査役会を設置していることは、企業が内部統制やガバナンス体制を重視している証となり、株主、投資家、取引先など外部からの信頼を得やすくなる。
【設置するデメリット】
監査役会設置会社のデメリットとして、下記が挙げられます。
1.最低でも3名以上の監査役が必要となるため、個々の監査役への報酬や、監査役会の運営にかかる事務的な費用が増大する。
2.取締役会での議決権を持たないため、直接的な経営の意思決定には参加できない。
3.監査役会設置会社は日本独自の設計のため、一部の海外投資家からは理解されにくく評価が低い傾向にある。
b.監査等委員会設置会社(監督強化型)
取締役会の監督機能を強化するため、2015年の会社法改正時に導入された新しい形態です。近年、この形態に移行する上場企業が増えています。また、本形態では取締役会の中に監査等委員会を設置するため、委員は取締役であり、「監査役」は存在しません。
監査等委員会を設置する際には、以下の構成を満たす必要があります。
・監査等委員である取締役が3名以上必要(会社法第331条第6項) ・そのうち過半数は、社外取締役でなければならない(会社法第331条第6項)
※常勤の監査等委員の選任義務を定めた条文はありません。 |
【設置するメリット】
監査等委員会設置会社のメリットとして、監査役を置かずに済むため役員の人数を削減できます。
例えば、監査役会設置会社(非大会社の場合)では取締役3名、監査役3名で、最小合計6名の役員が必要となるのに対し、監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役3名(うち2名以上が社外取締役)と業務執行をおこなう取締役1名で、最小合計4名の取締役での構成が可能です。
ただし、監査等委員会設置会社は会社規模にかかわらず会計監査人※の設置が必須となる点、また、会社の規模や事業内容、上場市場の要請(コーポレートガバナンス・コードなど)によっては、それぞれの機関設計で構成人数が増える場合があります。
その他に、下記のメリットも挙げられます。
1.常勤監査役のような常勤の人を設定しなくてもよい。
2.取締役の過半数が社外取締役等の条件を満たしていると、重要な業務執行に関する決定を特定の取締役に委任でき、経営に関する迅速な意思決定が可能となる。
3.議決権を持つ取締役で構成されるため、取締役会でも他の役員に対して直接意見したり投票したりすることも可能(監査役は、取締役会の議決権を持たない)。
議決権を持っているからこそ実効性の高い監督が期待でき、海外投資家からも「分かりやすい」と高く評価される傾向にあります。
【設置するデメリット】
監査等委員会設置会社のデメリットとして、下記が挙げられます。
1.監査役の任期が原則4年であるのに対して、監査等委員である取締役の任期は原則2年である。
2.専門知識と経験、そして独立性を持った社外取締役を見つけること自体が容易ではない。
3.一般的に、社外監査役よりも社外取締役の方が報酬水準が高い傾向にあるため、役員報酬総額が増加する可能性がある。
【Tips】
実際に、①〜③の監査体制の中でも、上場企業の多くが「①監査役会設置会社」か「②監査等委員会設置会社」を選択しており、特に監査等委員会設置会社は年々増加傾向※にあります。
※各委員会の採用比率の推移はこちら
①監査役会設置会社(2017年時点で75.3% → 2024年時点で55.2%) ②監査等委員会設置会社(2017年時点で22.6% → 2024年時点で42.3%) ③指名委員会等設置会社(2017年時点で2.1% → 2024年時点で2.5%)
|
(※各委員会採用比率の推移をグラフにしています)
c.指名委員会等設置会社(監督・執行分離の米国型)
経営の「監督」と「業務執行」を明確に分離し、経営の透明性を最大限に高めることを目的とした形態です。指名委員会等設置会社は、前項で述べた監査等委員会設置会社よりも歴史が長く、2003年に施行された商法改正によって「委員会設置会社(当時の名称)」として導入されました。
また、指名委員会等の「等」には、「報酬委員会」と「監査委員会」が含まれます。
指名委員会等設置会社はその制度上、必ず「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」の三つの委員会を設置することが義務付けられています。そのため、「等」にはその二つの委員会が含まれると考えられます。
指名委員会等を設置する際には、各委員会(前述の指名委員会・報酬委員会・監査委員会)で以下の構成を満たす必要があります。
・各委員会は、委員である取締役が3名以上必要(会社法第400条第1項) ・各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない(会社法第400条第3項)
※常勤の委員の選任義務を定めた条文はありません。 |
監査等委員会設置会社に比べると、指名委員会等設置会社の方が監査体制が強固に見えるかもしれません。しかし、前述のTips『各委員会の採用比率』でも記載の通り、指名委員会等設置会社の採用比率は全体の2.5%と少数に留まっています。
改めて、指名委員会設置会社のメリット・デメリットを解説します。
【設置するメリット】
指名委員会設置会社のメリットとして、下記が挙げられます。
1.独立した3つの委員会(指名委員会・報酬委員会・監査委員会)を設置するため、経営陣の選解任や報酬決定といったプロセスの透明性が向上する。
2.取締役会が「監督」に徹し、業務執行の決定権限を「執行役」に委任できるため、意思決定が迅速になる。
3.不正防止のためのルール作り、リスク管理体制の構築が強化されるため、内部統制機能が向上する。
【設置するデメリット】
指名委員会設置会社のデメリットとして、下記が挙げられます。
1.独立した3つの委員会(指名委員会、報酬委員会、監査委員会)を設置・運営する必要があるため、他の監査体制に比べると運営コストが高くなる。
2.前述の3つの委員会は、各委員会で最低3名以上の委員(うち2名は社外取締役)で構成されなければならない※。社外取締役の確保自体、容易ではない。
(※2名の社外取締役が3つの委員会を全て兼任することで要件は満たせますが、実務上はかなりの負担になり、実効性の観点からも推奨されません。)
4.最後に
本稿では、監査役の役割や、監査役会・監査等委員会・指名委員会等の役割、設置要件など基本情報と全体像を解説してまいりました。今回挙げた委員会以外にも、コンプライアンス委員会やリスクマネジメント委員会など、様々な委員会を設けている企業もあります。
本稿で触れることができなかった内容については、別途記事にて紹介予定です。ぜひご覧ください。
各種法令の参照元:e-gov法令検索
執筆:FUNDOOR
監修:当社関係 弁護士による監修 ※法人名、個人名に関しましては、直接のお問い合わせを避けるため非公開とさせていただきます。
担当弁護士からの一言コメント:自社に最適かつ実効的なガバナンスを構築するため、最適な形を選択し運用する必要があります。最適な形を選択することが、企業の持続的な成長に繋がり、ひいては社会からの信頼獲得にも繋がりますので、ご検討ください。